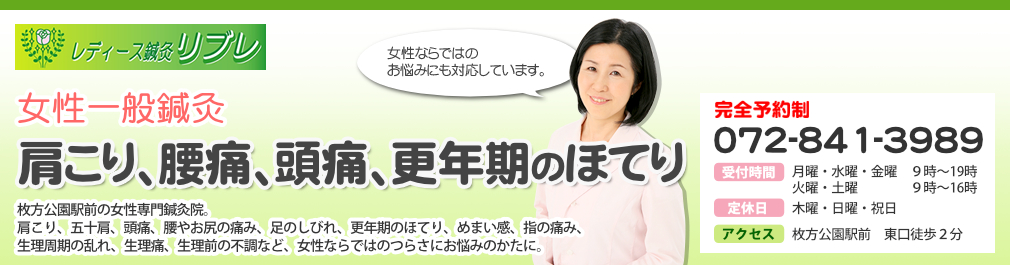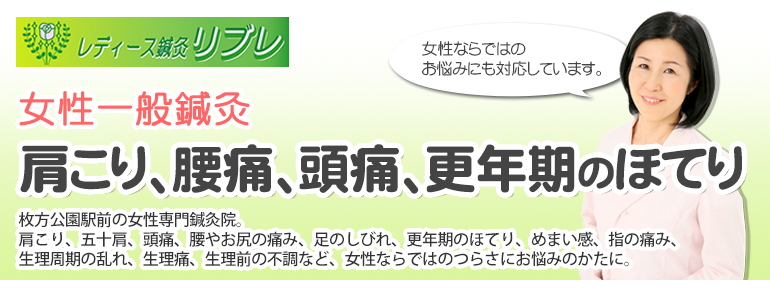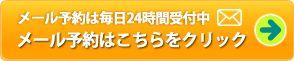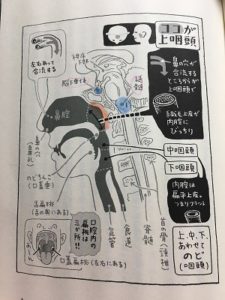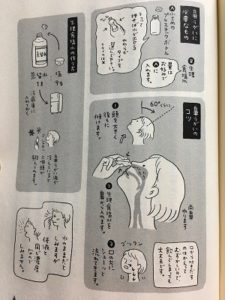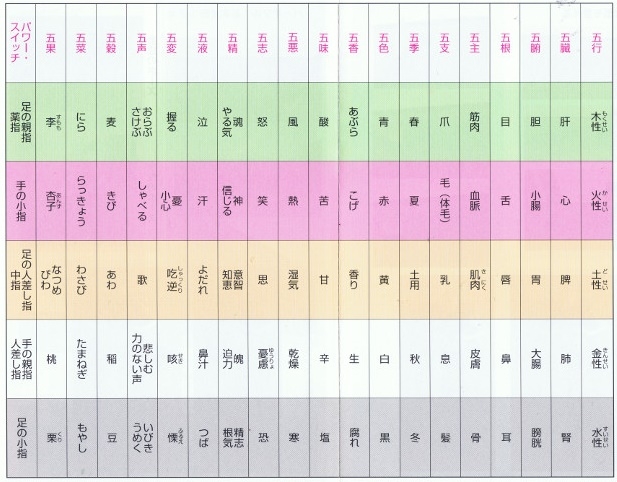自分に優しくする
この3ヶ月ほど、生活の変化、社会の変化に必死についていき、気を張って過ごしてきました。
やっとホッとできるかなぁという頃に、健康問題が出てきます。
運動会が終わった翌日に熱が出る、というあのパターンです。
この頃、鍼灸に来られた翌日、だる眠くなる方が増えています。
ご自分で感じている以上に、緊張して過ごしていて、疲れを押さえ込んでいたのですね。
緊張を緩めると、体の突っ張りがなくなって、力が入らない感じになります。
できれば、眠れるだけ寝てもらえると、疲れが抜けて元気になります。
カゼの病み上がりと一緒で、そこで無理をすると、また不調を押し込めることになります。
でも休めない状況の方は、どうすればいいのでしょう。
2つの方法をお伝えしますね
①全身をやさしくなでる
犬や猫、ハムスターなんかをうっとりさせるように、ふんわりと愛情をこめて。
縮んでいる筋肉をなでていくのがコツです。
- 耳の上の側頭筋
- ほっぺたの咬筋
- 鎖骨の下の胸筋
- みぞおちから足の付け根にかけて
- 太ももの後ろ側
- ふくらはぎ
フルコース行っても良いし、何かをしながら一カ所でもいい。
手に力を入れずに、気持ちのいいところをナデナデしていると、ほぁ~んと緊張感が取れて眠くなります。
時には、「こんな風に優しくされたかったんだなぁ」と涙ぐんでしまうことさえあります。
寝る前には、気持ちの良い場所にかすかに(←ポイント)手を当てて、深呼吸すると、いっそう緩んで深く眠れます。
②自分をほめる
上向きに寝て、リラックスして深呼吸しましょう。
体の力が抜けない時は、息を吸いながら体の一部分に力を入れて、一気に息を吐いて脱力します。
右足、左足、お腹、胸、右腕、左腕、右手、左手、顔は口と目をギュッとつむって緩める。
このとき、手のひらは上に向けておいてくださいね。
脱力できたら、自分に語りかけます。
「今日もたくさんのことを考えました、脳みそさん、お疲れ様でした。
いったん、そのはたらきを止めて休みましょうね。」
「今日もたくさん感情が動きました、心さん、ありがとう。
今はイライラも不安も感じなくて大丈夫、安らぎましょうね。」
「今日もたくさんの用事をしました、体さん、よく頑張ったね。
眠っている間に、疲れを取りましょうね。」
そして、思考と感情を止めて、自分の意識(魂の部分)だけ感じてみましょう。
思考でガチャガチャ、感情でザワザワされない、安らかな存在です。
大宇宙につながっている命です。
これを感じてから眠ると、癒されますよ。
これからも緊張感のある生活は続きます。
自分をリラックスさせる方法を身につけて、本当の危機に対処できる余裕をもっておきましょう。
ネット予約はこちら!(外部サイトへ飛びます)
https://www.shinq-yoyaku.jp/salon/2270
枚方公園駅前 レディース鍼灸リブレ院長