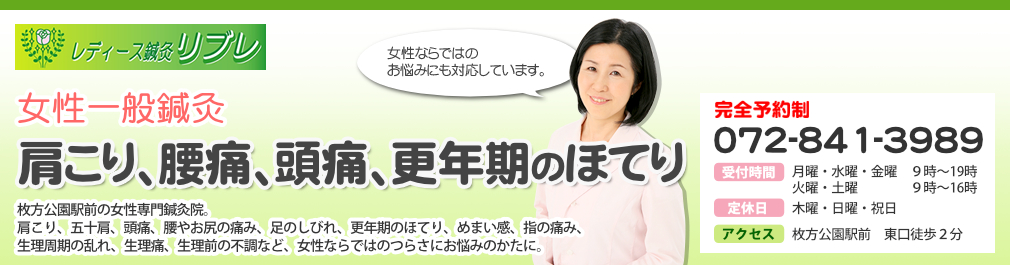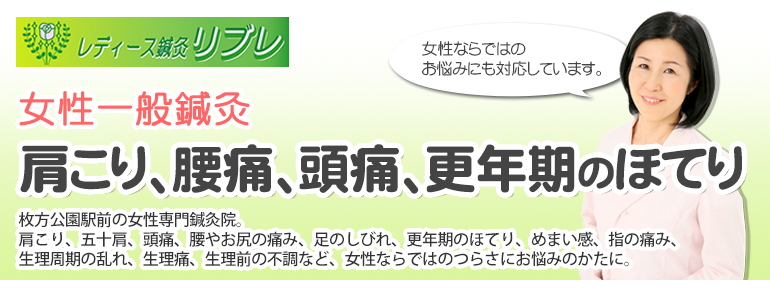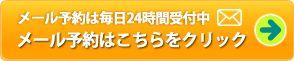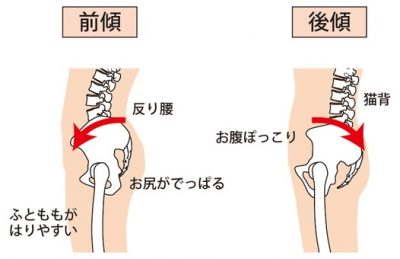突然のだるさは少陽病の可能性
「少陽病」はカゼの一種ですが、西洋医学にはない概念です。
陽病は内臓まで侵されてない状態、陰病は内臓に影響が出る状態、少陽病は「これ以上無理すると、内臓まで悪くしますよ」という警告です。
カゼの治りかけでグズグズ長引いたり、カゼをひいた記憶はないのにインフルエンザ後のようなしんどさを感じる状態です。
軽めのカゼを追い出す体力がない時におきます。
また、普段からイライラすることの多い人が、カゼをひきかけた時、カゼをこじらせた時になります。
症状としては、食欲がない、昼も夜も眠い、だるい、咳が出る、のどがガサガサする、何となくイライラする、午後から夕方になると熱っぽい、など。

この全部が当てはまらなくても、いくつかあれば少陽病かもしれません。
それ以上ひどくはならないので、様子をみていても全然よくなりません。
病院へいくと、「炎症はたいしたことないです。細菌かウイルスか判断するのに、いろいろ薬を変えてみましょう」ということになりがちです。
解熱剤はこの頃、使わない医師が増えましたが、体力が落ちているときに薬で熱を下げると、熱は体の深い所にひそんでしまいます。
この熱が内臓の働きを落として、だるさや眠気のなります。
熱はじわっと出る汗で追い出すのがベスト。
おへそから下、腎臓(ウエストの高さの背部)をホットタオルで10分くらい温め、上半身から汗が出るのを待ちましょう。
すぐに出なくても、何度かやって、寝ている時に汗が出てもOK.
温かいスープやシナモンティーもいいですね。
長風呂は疲れるので、ほどほどに。
汗をかいたら、その日と翌日くらいは、ゆっくり休んでください。
ここ重要です!
無理すると内臓にくるか、自律神経にきますので。
カゼは万病のもとですよ~
予約はこちら
https://www.shinq-yoyaku.jp/salon/2270/(別サイトへ飛びます)
枚方公園駅前 レディース鍼灸リブレ 院長